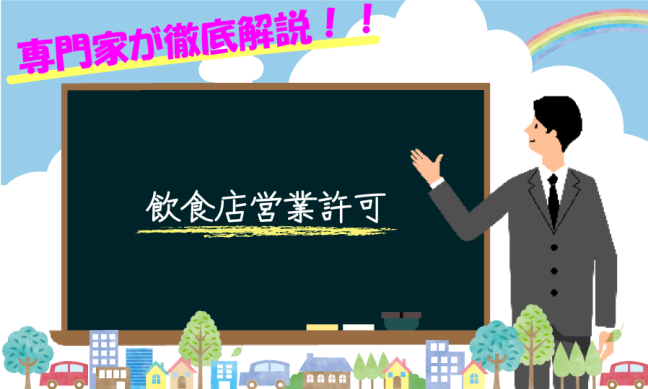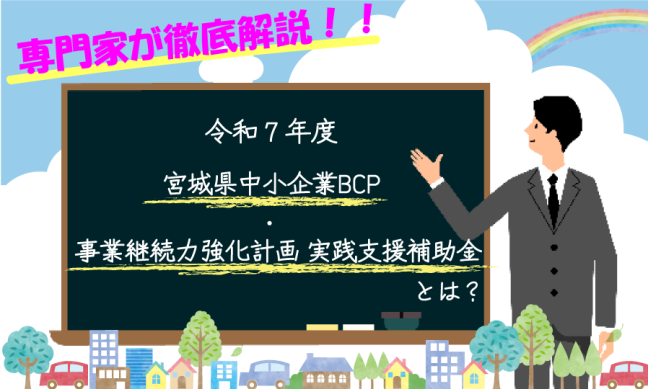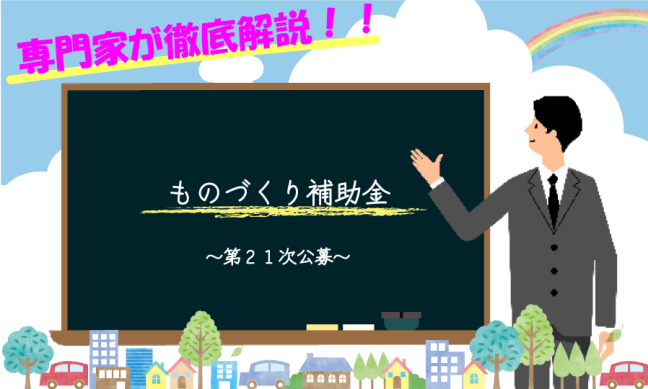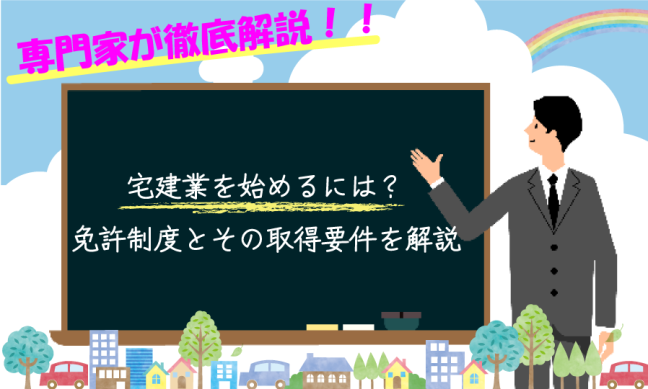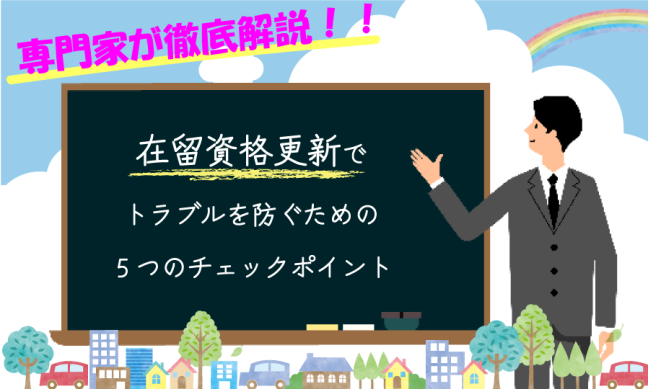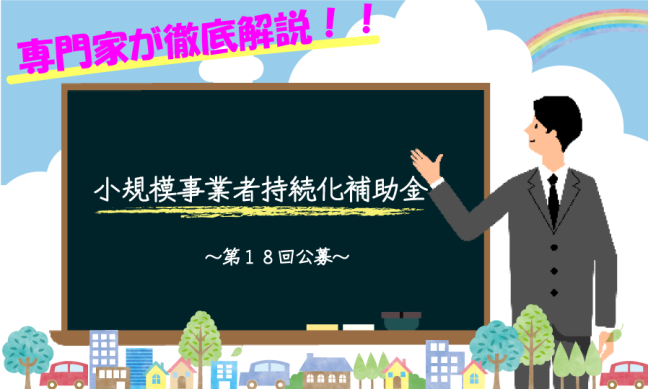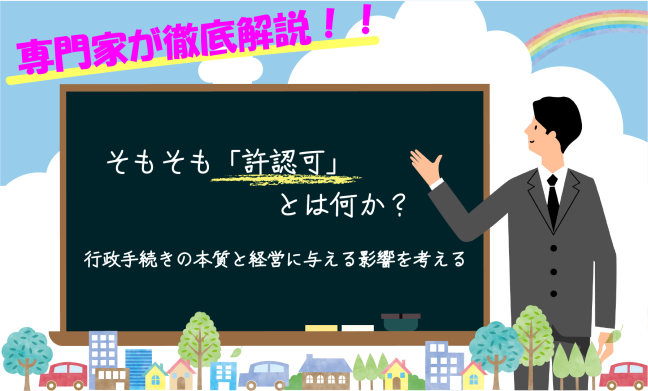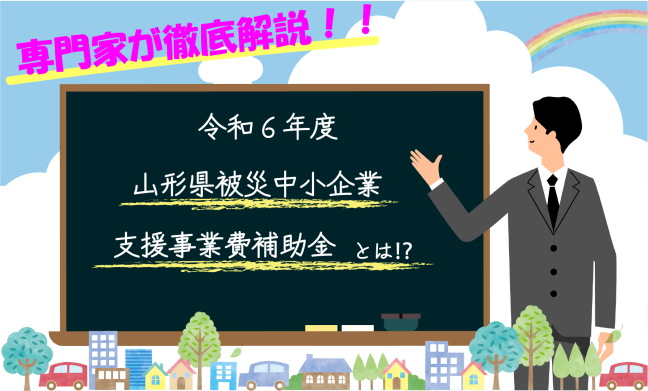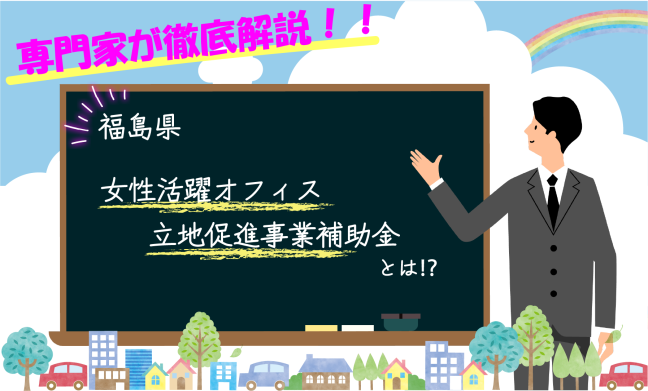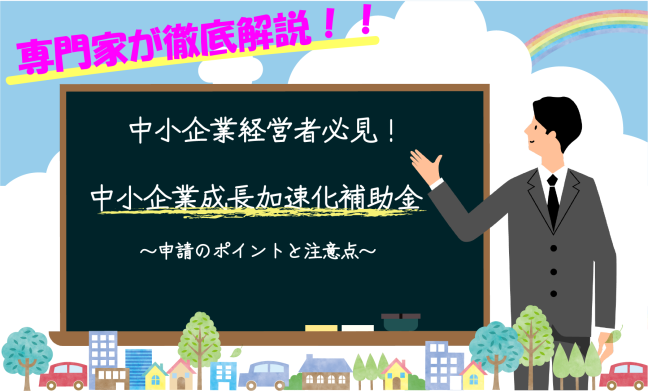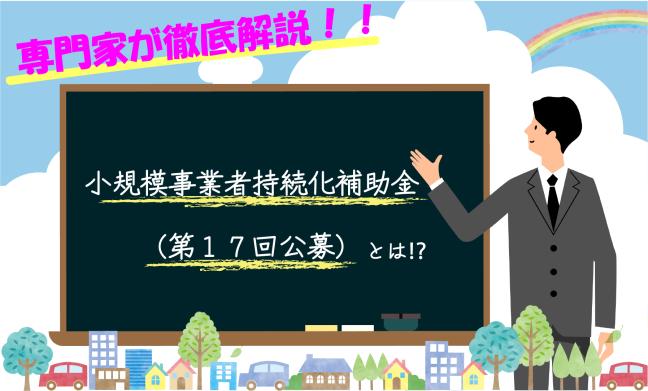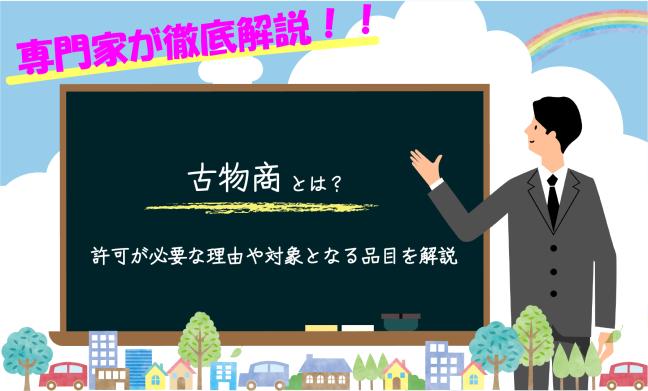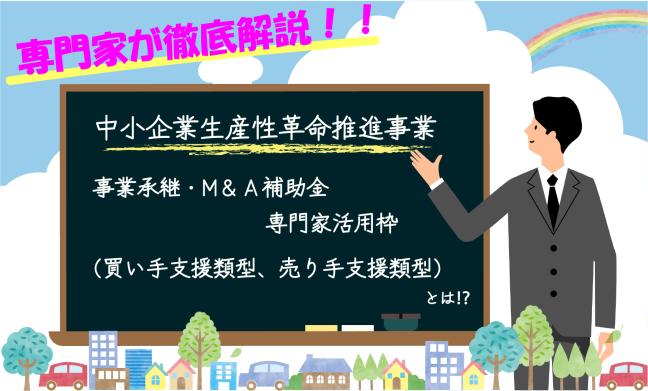専門家が徹底解説!経営所得安定対策とは⁉
- 補助金・助成金
- 事業に役立つ情報が知りたい
- 新しい事業を始めたい
掲載日:2024年4月12日

経営所得安定対策
農家は我が国の食=生存の根本を支える大きな役割を担っているにもかかわらず、その収入が需要と供給のバランスや天候、更には国際情勢にも大きく左右され、安定しません。
経営所得安定対策は、担い手農家の経営の安定を支えるため、諸外国との生産条件の格差から生じる不利を補正する交付金(「ゲタ対策」)と、農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティーネット対策(「ナラシ対策」)です。
対象エリア
全国
制度の対象者
認定農業者、認定新規就農者、集落営農(規模の要件はありません)
認定農業者でない農家がこれらの制度を利用する場合には農業経営改善計画等を作成した上で「認定農業者」になる必要があります。
同様に「認定新規農業者」でない新規就農者は青年等就農計画を作成して認定新規農業者になる必要がありますし、「集落営農」とされるためには組織の規約を作成したり作物に関する共同販売経理を行う体制を構築する必要があります。
1.畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
農作物の販売収入に対してゲタを履かせることで生産費割れの状況を防ぐ、という意味で「ゲタ対策」と呼ばれています。
畑作物は海外と比較しても日本での生産条件は不利であるため、外国産の畑作物に押されることで担い手農家の生産費割れを招く事態が発生します。
それを補うために対象となる作物の清算と販売を行う担い手農家に対して交付金を給付する制度がこの畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)です。
「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接農家へ支払う制度です。
|
①対象農産物 |
麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね |
|
②支払い方法 |
生産量と品質に応じて交付する「数量払」を基本とし、当年産の作付面積に応じて交付する「面積払」は数量払の先払いとして支払われます。 交付単価は(現時点。3年ごとに見直されます)、面積払が10アールあたり2万円、数量払いが例えば小麦の場合は60kgあたり5,930円(課税事業者の場合。免税事業者は6,340円)、大豆の場合は60kgあたり9,430円(課税事業者の場合。免税事業者は9,840円)です。 |
2.米・畑作物の収入減少影響緩和交 付金(ナラシ対策)
畑作物に「米」を含めた農業収入全体の減少に伴う影響を緩和するための制度が米・畑作物の収入減少影響緩和交付金です。
米や畑作物は価格や収量が変動しやすく農業収入が一定しません。農家が積み立てた拠出金を備えておいて、収入が大きく落ち込んだ場合にそれを補てんすることで変動を「ならし」ます。このため「ナラシ対策」と呼ばれています。
農家拠出を伴う経営に着目したセーフティーネットであり、米及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための保険的制度と言えます。
| ①対象農作物 | 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ |
| ②支払い方法 |
農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計(当年産収入額)が、標準的収入額を下回った場合にその差額の9割が補填されます。財源は農家の積立金と国が1:3です。 基準となる数字ですが、「標準的収入額」は直近5年の収入額のうち、最高年と最低年を除いた3か年の平均収入額で、品目ごと、地域ごとに計算しています。各年産の収入額は、米であれば、地域の産地品種銘柄のうち、数量の多い上位3銘柄平均販売価格に、地域の実単収を乗じて算出します。 「当年産収入額」は当年産の収入額として、品目ごと、地域ごとに計算しています。当年産の収入額は、米であれば、当年産の地域の産地品種銘柄のうち、数量の多い上位3銘柄平均販売価格に、当年産の地域の実単収を乗じて算出します。 この「ナラシ対策」と類似した制度で農業共済組合による「収入保険」がありますが、どちらか一方を選択して加入することができます。 |
申請のポイントと行政書士からひとこと
会員登録している方のみ
続きをお読みいただけます。