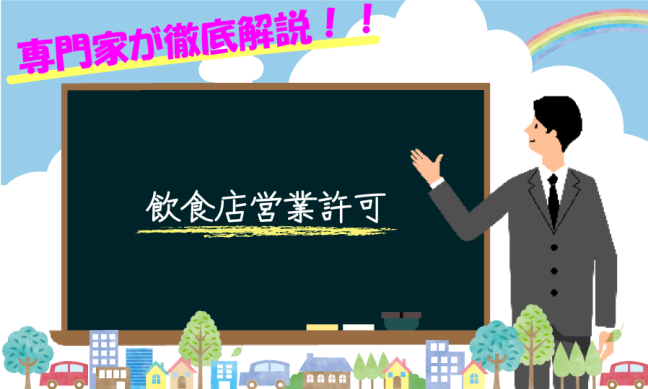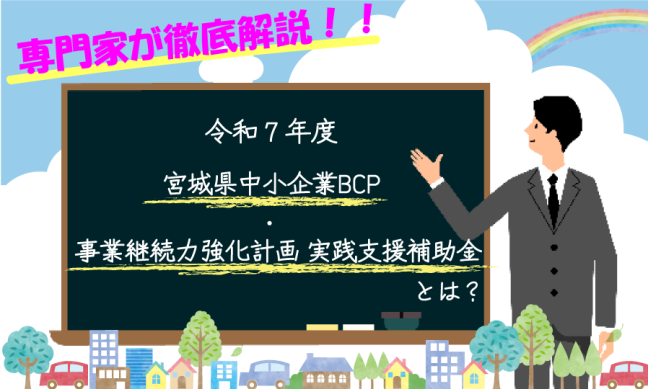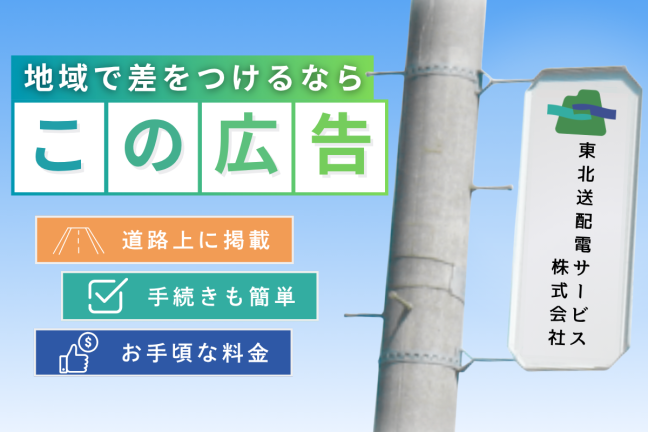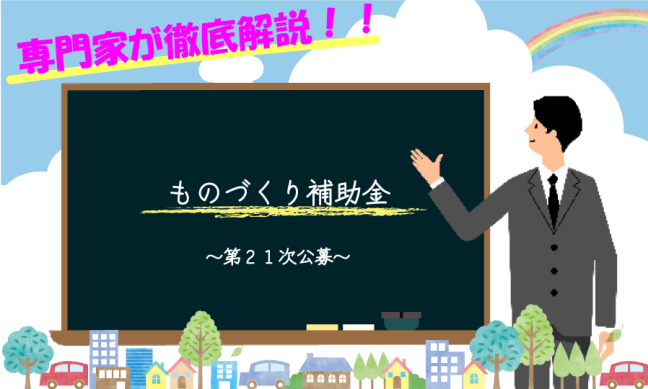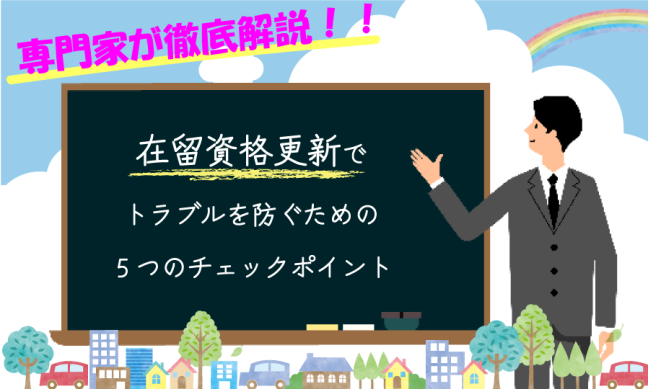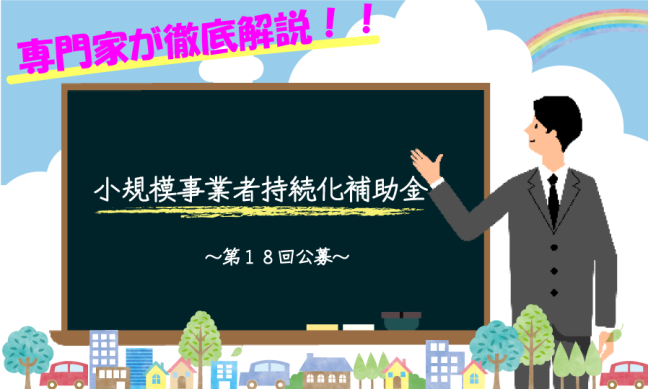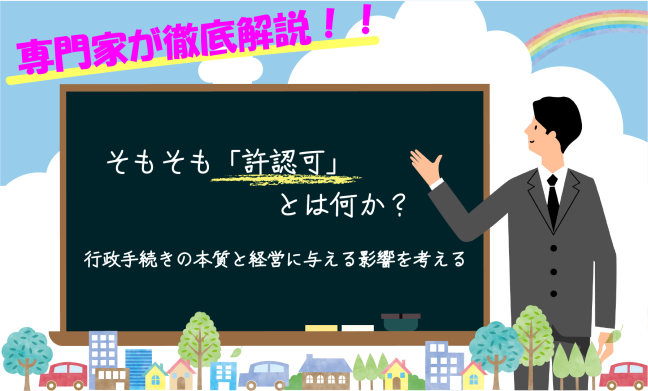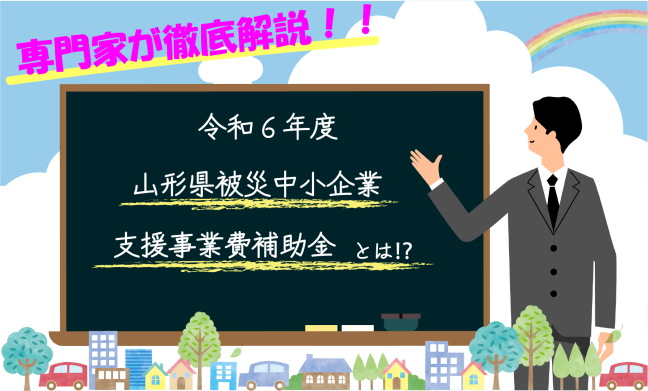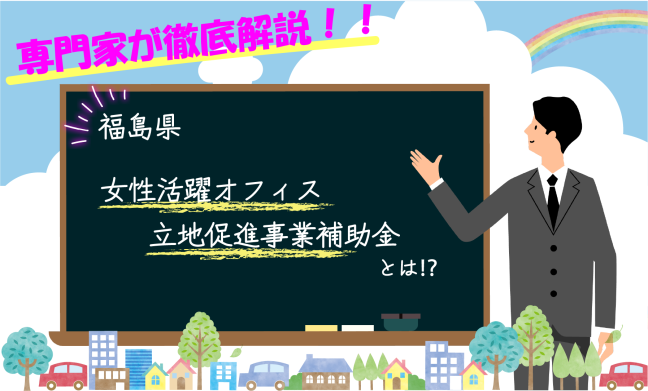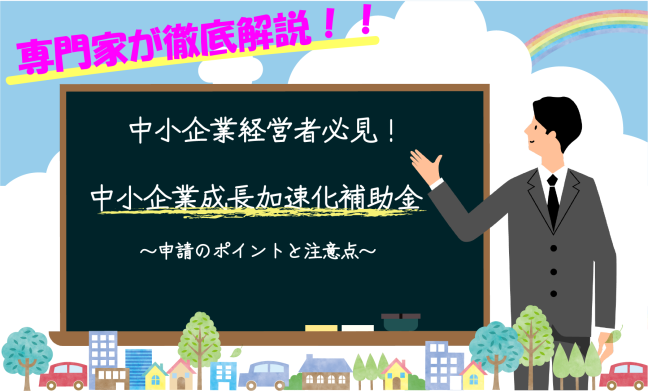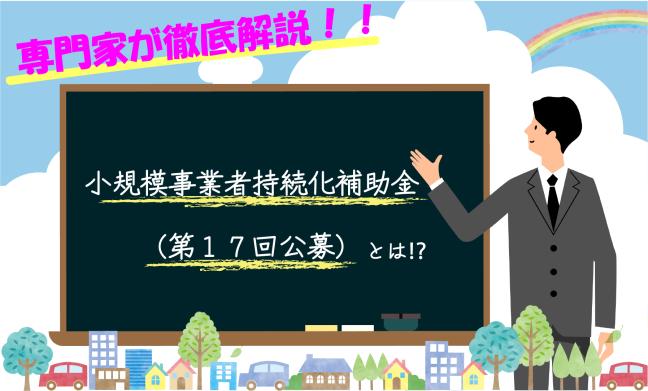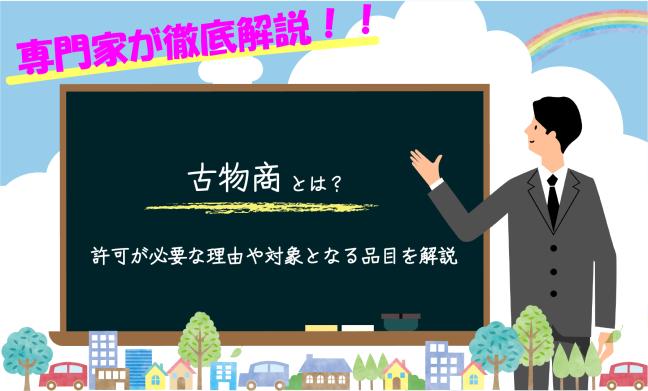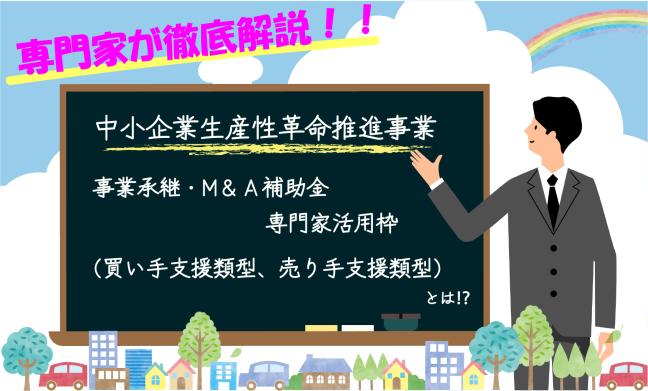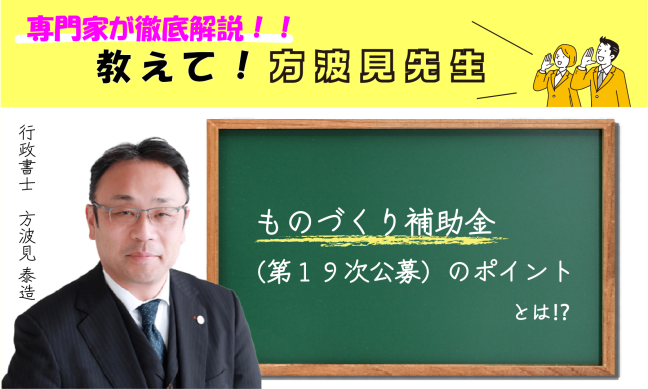【専門家が徹底解説!】宅建業を始めるには?免許制度とその取得要件を解説
- 補助金・助成金
- その他のテーマ
- 事業に役立つ情報が知りたい
掲載日:2025年9月16日
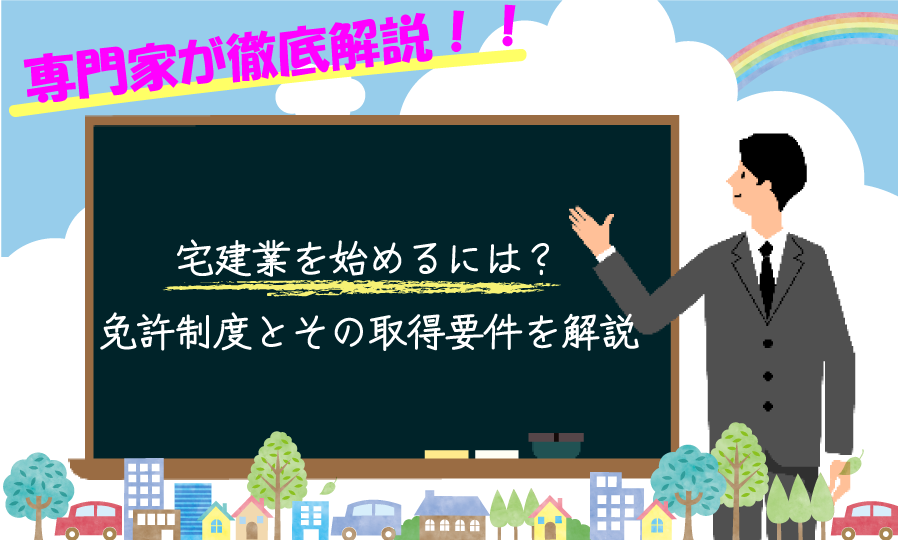
宅建業の開始には「免許」が必要
土地や建物といった高額な資産を扱う「宅地建物取引業(宅建業)」を営むには、事前に所定の免許を取得する必要があります。
免許は、営業所の所在地によって取得先が異なります。
複数の都道府県に事務所を構える場合は国土交通大臣免許、単一の都道府県内のみで営業する場合にはその都道府県知事の免許が必要です。
この免許制度は、不動産取引の透明性を確保し、購入者を保護するために設けられています。免許の有効期限は5年で、継続して事業を行うには更新手続きが必要です。
宅建業免許が必要な取引とは?
宅建業の免許は、一定の不動産取引を「業として」行う場合に求められます。
ここでの「業として」とは、営利目的で不特定多数の相手に対して、継続・反復的に取引を行うことを指します。
必要な取引の種類
| 取引内容 |
自己物件 |
他人の物件(代理) |
他人の物件(媒介) |
|
売買 |
必要 |
必要 |
必要 |
|
交換 |
必要 |
必要 |
必要 |
|
賃貸 |
不要 |
必要 |
必要 |
※「媒介」とは、いわゆる「仲介」を意味します。
免許が不要なケースは、例えば自社所有の賃貸物件を貸し出す場合(例:賃貸アパートの大家)、賃貸物件の管理業務、サブリース契約(ただし、形態によっては宅建業に該当する場合もあるため要確認)等です。
宅建業免許を取得するための要件
宅建業を営むには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 業務を遂行できる体制の整備
各営業所には、取引契約を締結できる責任者(使用人)を配置する必要があります。
- 宅地建物取引士の設置
営業所ごとに、従業員の5分の1以上の割合で「専任の宅地建物取引士(旧:取引主任者)」を配置する義務があります。
- 営業保証金の供託または保証協会への加入
免許取得後、営業を開始するには以下のいずれかの方法で資金の供託が必要です。
【供託の場合】
主たる事務所:1,000万円
従たる事務所ごとに:500万円
【保証協会へ加入の場合】
主たる事務所:60万円
従たる事務所ごとに:30万円(弁済業務保証金分担金として納付)
事務所に関する基準(例:宮城県)
宅建業では、事務所の設置条件にも細かな規定があります。以下は宮城県の基準例です。
■ 基本要件
・他の事業者と物理的に独立していること
・出入口が専用で、他社の区画を通らずに到達できる構造であること
・パーテーション等でしっかり間仕切りされていること(高さ180cm以上)
■ 自宅の一部を事務所とする場合
・事務所と住居が明確に区分されていること
・共有スペース(台所・居室など)を通らずに行き来できる動線が確保されていること
・外観・内部ともに事務所としての体裁が整っていること
■ マンションを利用する場合
・専ら事務所利用であるか、住居との機能が明確に分離されていること
・規約上、事務所使用が許容されていること
まとめ

特に事務所形態や営業保証金の供託、取引士の配置など、細かな条件を事前にクリアしておくことが、スムーズな開業への鍵となります。
今回もハイフィールド行政書士法人 方波見先生より解説いただきました。
本記事についてのご相談や、その他許認可や補助金にお困りの際には、
方波見先生へお繋ぎいたしますので、お気軽にご相談ください。
|
<サービス提供者について> |