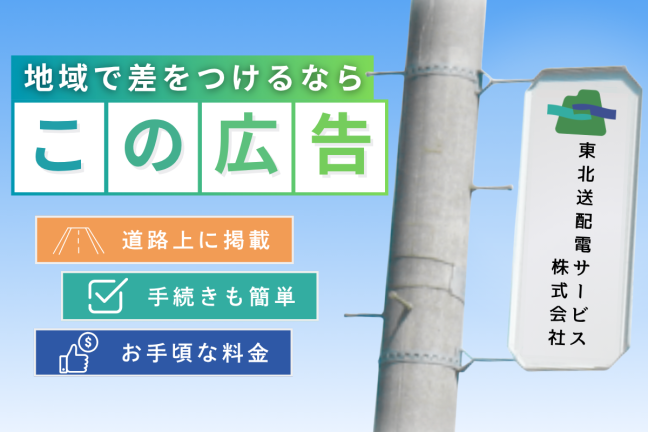『CONNECT+』Vol.4: 特集ページ(西川町長対談)
- イノベーション・共創
- 地域活性化・地域課題解決
- ICT・DX
- CONNECT+
掲載日:2024年3月29日

「デジタルとフィジカルの二刀流」
~限界目前ローカルが生き残るために~
山形県のほぼ中央に位置する西川町(にしかわまち)。
朝日連峰や月山と支脈に囲まれ、総面積の95%は山地が占める。
人口4,956人(令和2年国勢調査)の小さな町が、デジタルの活用で今注目を集めている。
地方創生の限界点が目前に迫る中で、町が取り組んでいるのはデジタルとフィジカルのいわば二刀流。
その戦略的な取り組みについて、菅野大志(かんの・だいし)町長に狙いや思いを伺った。
「戦略的なデジタル住民票の活用」
町の“デジタル住民”だと証明するNFTで、保有者は菅野町長が参加するオンラインコミュニティに入会できるほか、町内の温泉の入浴無料といった特典を受けられる。
販売数1,000に対し、13,440もの申し込みがあった。
NFTとは「偽造できない鑑定書・所有証明書付きのデジタルデータ」のこと。
簡単にコピーや改ざんができる従来のデジタルデータの弱点を克服し、価値を証明できるようになったものだ。
NFTによってデジタルアート作品等が高値で取引されるようになり、近年注目を集めている。
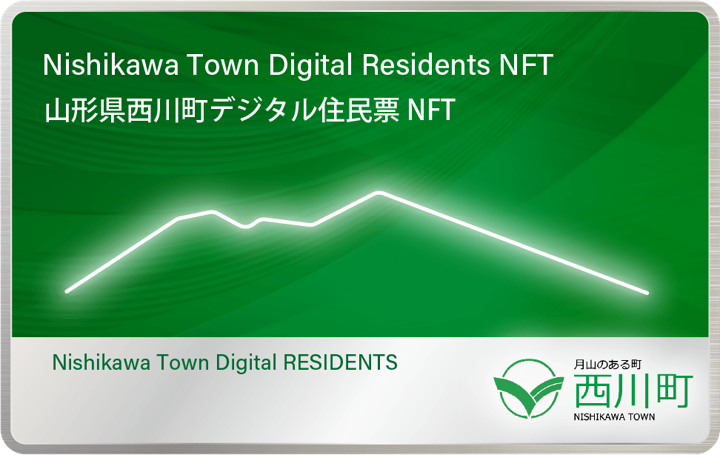
デジタル住民票NFTを発行した狙いは、若年層と富裕層にターゲットを絞った、関係人口の創出にある。
民間の調査会社によると、NFTユーザーは年代別では20代が最も多く、投資への関心が高いという特徴がある。(ロイヤリティ マーケティング調査より)
発展途上のNFTに“理解のある自治体”としてNFTユーザーから注目された結果、町の人口の2.8倍もの申し込みを集めることに成功したのだ。
昨年11月には、町のデジタル住民を対象に東京で交流会を開催。
町長をはじめ、町民38名もボランティアとして駆け付けた。
デジタル住民と町民、デジタル住民同士の交流が生まれ、町の魅力をリアルに感じてもらう機会となった。
「対話の場でフィジカルを体現」
デジタル施策と対をなすのが、フィジカルな施策だ。
菅野町政で新設された「つなぐ課」が所管する、町民との対話の場。
毎月テーマごとに担当課との対話会と、地区ごとに町長との座談会を開催し、あわせて年間60回以上にも及ぶ。
周知文には、「ごちゃまぜになって、対話しましょう!ときには腹を割って話し、またつながり合い、そこから西川のミライや実施すべき事業が見えてきます」とある。
周知ツールにはLINEのオープンチャットを活用し、参加のハードルと行政コストの両方を下げている。

対話を重視する背景には、町長の「地方自治の根幹は住民が幸せであること」という考えがある。
町長や町職員がやりたいことの前に、町民がやりたいことがある。
しかし、予算や経営資源といった条件があり、全てを実現することは難しい。
そこで、町民のニーズを知り、それらをどう実現していくか考えるために、対話の場を設けているのだ。
町の財政のために掲げた「予算6原則」の1つ目には、「ニーズベース」がある。
対話しなければニーズは把握できず、解像度も上げられない。
対話を重視する意志は“対話に積極的な職員”だけが課長補佐以上になれるという、画期的な人事方針にも表れている。
「タイムリミット7年の挑戦」
2022年4月の選挙で初当選した菅野町長は、高校までを西川町で過ごし、大学進学を機に上京。
財務省東北財務局に入局し、金融庁では金融機関の監督業務や地域課題解決支援チーム等を経験した。
ふるさとに注目するきっかけとなったのは、内閣官房での仕事だった。
地方創生の限界点を示す調査で、「人口4.000人以下で、65歳以上が45%を超える自治体は、将来的な再生が極めて困難になる」という結果に衝撃を受けた。
西川町は、2030年に人口4,000人を割り込むと推計されていたからだ。
調査結果に触れたのは、2021年のこと。
「西川町が限界点を迎えるまで、あと7年。7年あれば、自分の経験と知識で何かできるのではないか。」
こうして菅野町政はスタートした。
まず取り組んだのは、予算の確保。財務省をはじめ5省庁を渡り歩いた経験を生かしつつ、様々な省庁の補助金を獲得してきた。
また、企業版ふるさと納税を活用し、企業と共に解決したい地域課題を明らかにすることで、寄付金を約18倍に増やした。
地元企業だけでは対応できない課題にも、全国からノウハウのある企業が手を挙げてくれることで、解決に取り組めるようになった。

2Dメタバースで地域交流の新たな形を提供
山形県道 の駅、月山湖、志津温泉などが再現されている

デジタル住民票NFT保有者限定で開催した、メタバース交流会
画面上で自身のアバターを操作することで他者と交流を行う
関係人口の創出等、トップダウンのほうが進めやすい政策はたくさんあった。
特に、国家公務員としてではなく、個人として構築してきたネットワークが大いに役立った。
スタートアップへの参画等、“部活動”と称し意識的に経験と人脈を広げてきた。そのネットワークから、町と直接関係のなかった個人や企業を繋ぐことに成功したのだ。
一方、この2年間で町職員の意識や行動が変化している実感もある。
各課がチームとなり、ボトムアップで施策が実現しつつある。
理想はティール組織。
町職員一人ひとりがチームの目的をはっきりと理解し、強いリーダーがいなくても、現場において必要な意思決定を行える状態が最強の組織だという。
その実現のためにも、やはり対話は欠かせない。
「生き残るための共創」
最後に、菅野町長が考える「共創」を問うと、「自立」という言葉が返ってきた。
人が1人でできることには限界があり、依存ではなく、各分野で頼れる人をすぐに見つけられる状態が自立であり共創なのだと。
32歳の時、東日本大震災を経験。当時は財務省の金融部門として、仙台で勤務していた。
経験のない大災害で多種多様な相談が寄せられたが、「それは財務省ではなく経済産業省の担当です」と回答してしまう場面があった。
目の前で困っている人がいるのに、自分は役に立たないと深く反省した。

上司の中には、所属に関係なく個人のネットワークで、寄せられた相談に対応している人もいた。
それまでは家族と地元の友人、同僚がいれば幸せだと思っていたが、個人の繋がりは重要だとハッとさせられたのだった。
何か解決したい課題に直面した際、個人でできることには限りがある。
信頼できる共創パートナーをいかに見つけるか、そこには良質なネットワークが欠かせない。
そして、良質なネットワークを構築するためには、日頃の対話や労力を惜しまない姿勢が大切なのだ。
こうした経験から生まれた、デジタルとフィジカルの二刀流。
西川町がどう限界を突破していくのか、今後も目が離せない。
インタビューの全編動画を会員限定で公開中!
▼ ご興味のある方はぜひご覧ください ▼
『CONNECT+』ではいろいろな情報を発信していきます。
会員登録は無料ですので、まだの方はぜひこの機会にご登録ください!
|
<サービス提供者について> |