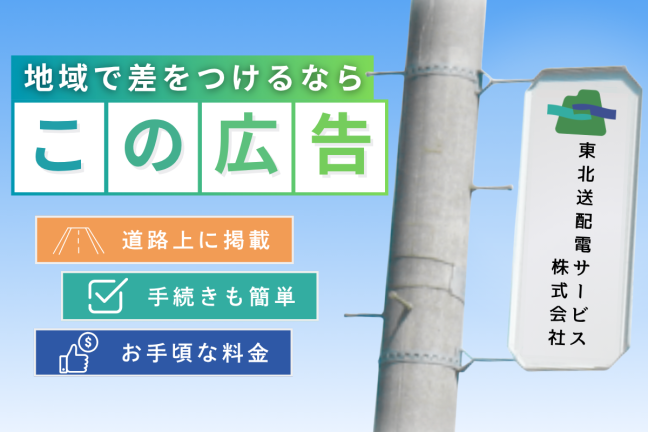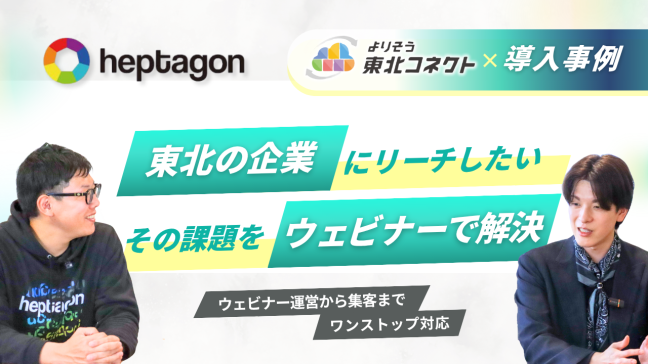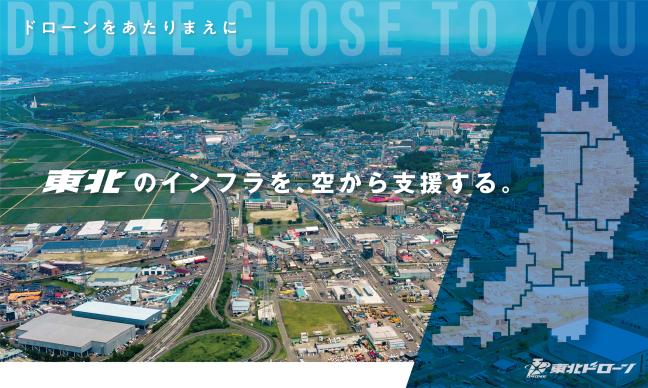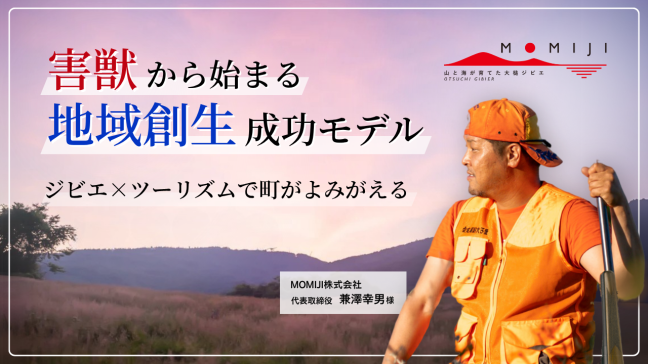『CONNECT+』Vol.9:特別インタビュー
- 地域活性化・地域課題解決
- イノベーション・共創
- CONNECT+
- 東北・新潟の地域活動や社会貢献活動に参加したい
掲載日:2024年10月28日

DAO&NFTがローカルコミュニティを救う
リアルとデジタルの融合で追求する、新たなローカルコミュニティ
人口約720人が住む地域に、1,700人を超える“デジタル村民”が集まっている山古志村(現新潟県長岡市山古志地域)。
2021年、地域住民などの有志が集まる「山古志住民会議」の3代目代表・竹内春華さんが中心となり「仮想山古志村プロジェクト」が推進されている。
同プロジェクトでは電子住民票の意味あいを含んだ「Nishikigoi NFT」(NFT:非代替性トークンを意味するデジタル資産)を発行し、購入者には電子住民票も付与。デジタル村民は山古志の仲間としてさまざまな活動に参加し、約3割が山古志に足を運んだ。

©ykxotkx's works Carp and Seasons
こうした山古志の“リアル”と“デジタル”の垣根を越えた動きは「山古志DAO」(DAO:分散型自律組織)として盛り上がりを見せ、地域活性化を目指すローカルにとってモデルケースとなる可能性を秘めている。
NFTを通じて国内外から“1,500万円”の想いが寄せられた
2021年10月から始まった「仮想山古志村プロジェクト」は、デジタルの場に「人」「モノ」「お金」「情報」が継続的に集まるコミュニティを形成し、山古志の地域課題の解決策を現地の住民と検討し地域活性化を実践する施策だ。
Nishikigoi NFTの購入者は“デジタル村民”と呼ばれ、山古志住民会議における各種の意思決定に参加できる。チャットツール「Discord(ディスコード)」内にて、地域づくりを議論するコミュニティへのアクセス権も付与した。同NFTは、デジタルアートが描かれた電子住民票を付与した暗号資産としてEthereum(イーサリアム)で販売。ヨーロッパやアジアなど、海外にもファンをもつ山古志名産「錦鯉」をモチーフとしたデザインを採用する同NFTは、2021年12月・2022年3月に発行され約1,500万円(※)を売り上げた。
※当時のEthereumのレート

対談の様子
左, 雑談会議:稲垣 右, トークネット:赤城
その後、実施された「山古志デジタル村民総選挙」では、山古志の活性化を目指す12件のアクションプランから、投票により上位4件を選定。2022年上半期から各プランが始動し、Nishikigoi NFTの売上約1,500万円のうち100万円を各プロジェクトの予算とした。
同NFTの購入者の特徴は「山古志の運営に携わり、これからの山古志を良くしていきたい」という想いのある“ファン”が多いこと。人口約720人の地域に1,700人以上の“共感者”が集まり、うち2割は海外の購入者だ。
3年間の“全村避難”から未来への一歩
2004年10月に発生した新潟県中越地震の際に、「山古志村」の名を耳にした方もいるだろう。山古志村は大きな被害を受け、全村避難を余儀なくされた。2005年4月の“平成の大合併”により、山古志村は長岡市と合併した。

山古志村の被災当時について語る竹内氏
復興を目指す中で、2007年7月には住民が「自分たちが住む地域の未来は、自分たちで作ろう」という理念を掲げた住民団体「山古志住民会議」を設立。同会議は、今後の山古志の将来を見据え「やまこし夢プラン」を策定するなど、地域活性化に向けて活動を展開している。
その一員として、精力的に取り組んでいるのは新潟県魚沼市出身の竹内春華さんだ。全村避難した住民が入居する仮設住宅内で生活支援相談員として支援にあたり、その際に「山古志に戻ろう」と明るく前を見据えた住民の姿に心を動かされ、地域復興支援員として継続的に山古志へ携わるようになった。意欲的に活動する姿が住民から評価され、竹内さんは2021年4月から同会議の3代目代表として活躍中だ。
オープンマインドで世界の“仲間”を紡ぎたい
3年間の避難を経て、約2,200人の住民のうち約1,700人が山古志に帰還した。しかし、少子高齢化社会の影響を受ける中で、山古志の人口は2018年に1,000人を切る。その後も過疎化が続き、2024年10月現在の人口は約720名に減少。人口減少が進む状況下で、竹内さんは「なんとか山古志を守りたい」という強い想いを胸に、トライアンドエラーを繰り返す。
その過程で、竹内さんは「住民や協力者にとどまらず、山古志が発祥とされる錦鯉の海外ファンなど“山古志から離れて暮らす人々”が抱くこの地への想いも財産だ」と感じていた。当時を振り返り、竹内さんは「住民だけが地域を紡ぐ主体ではなく、山古志に1日でも1回でも支援していただいた方や想いを寄せていただいた方を“仲間”だと強く実感しました」と語る。
「世界から仲間を募ろう」と仕組みを模索する中で、竹内さんはリアル村民と山古志に共感する各地の人々がつながる「メタバース(仮想3次元空間)」の導入を検討した。しかし、当時は予算の折り合いがつかずに断念。さらに模索を重ね、竹内さんは地域づくりの活動で知り合った十数年来の友人である一般社団法人Next Commons Labの代表理事・林篤志さんに相談を持ちかける。林さんを通じてIT企業である株式会社TART(現NEORT株式会社)の代表・高瀬俊明さんと出会い、山古志での現地ヒアリングを経てNFTの導入に踏み出した。

山古志のデジタルコミュニティ
地域活性化の可能性を拓く“ネオ山古志村”モデル
山古志に共感して集まったデジタル村民とのコミュニティ形成が進む中、竹内さんはNishikigoi NFTの発行に端を発した取り組みが「DAOそのもの」という声を数多く耳にする。同NFTの発行を通じてデジタルとリアルの垣根を越えたコミュニティ形成を推進する山古志の取り組みは、確かにDAOと言えるだろう。山古志デジタル村民総選挙で選ばれたプロジェクトが推進し、デジタル住民とリアル住民の交流イベントも開催されている。
ローカルではさまざまな強みや役割を持った住民が集い、想いの具現化を目指し自律的に行動する。それもまさにDAOだ。山古志の先人たちも想いを結集し、厳しい自然環境の中で錦鯉を生み出し、新たな文化が醸成された。錦鯉の存在は海を越えて知られるようになり、山古志は多くのファンから“錦鯉の聖地”として親しまれている。
現代のローカルにとって、国内外でファンを集められるデジタルの仕組みは「想いを形にする新たな可能性」と言えるのではないだろうか。「山古志DAO」は進化し、今では「ネオ山古志村」と呼ばれている。魚沼市出身で、山古志にとって言わば“よそ者”の竹内さんは「生まれ育った魚沼、そして“ネオ山古志村”が私にとってのアイデンティティ」と語る。デジタル領域に縁遠い中で竹内さんは想いを胸に挑み続け、NFTを起点に可能性を拓いた。今もなお過疎に直面する山古志は、東北各地のローカルの“縮図”とも言える。ネオ山古志村の活動は、ローカルが地域活性化を実現する新たなモデルとなるのではないだろうか。

インタビューの全編動画を会員限定で公開中!
▼ ご興味のある方はぜひご覧ください ▼
『CONNECT+』ではいろいろな情報を発信していきます。
会員登録は無料ですので、まだの方はぜひこの機会にご登録ください!
|
<サービス提供者について> |