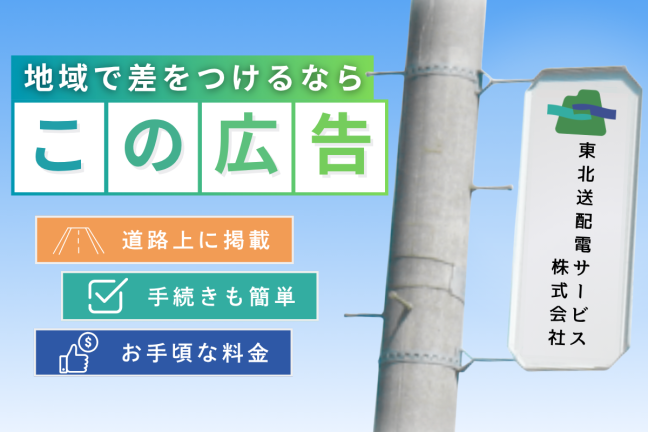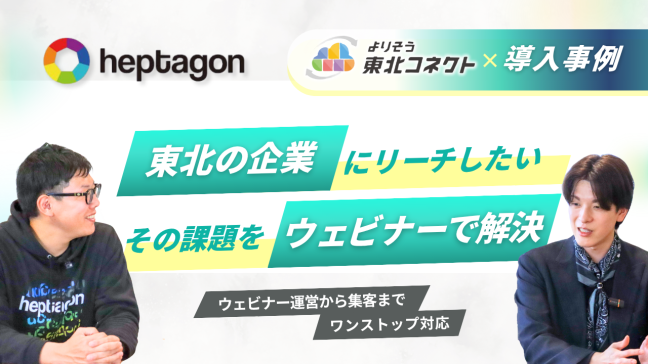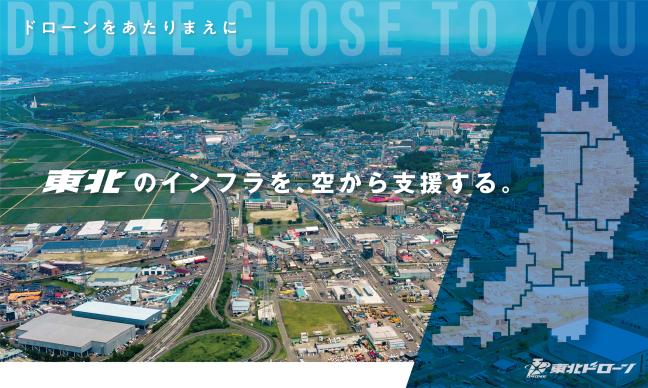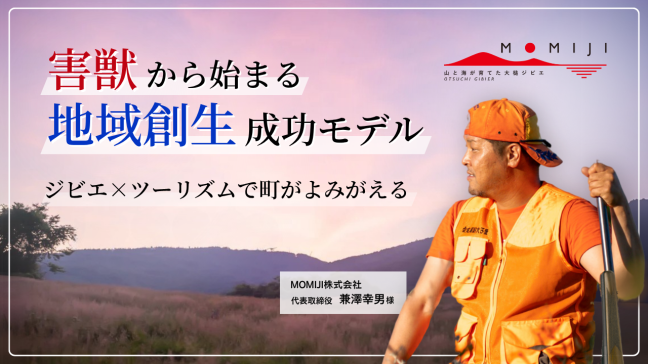『CONNECT+』Vol.15:地域企業の突破口
- 地域活性化・地域課題解決
- イノベーション・共創
- 東北・新潟の地域活動や社会貢献活動に参加したい
- CONNECT+
掲載日:2025年9月5日

地域企業の突破口
~共創からはじまるInnovation~
「共創」は企業にどんな変革をもたらすのでしょうか。
地域企業が成長し続けるためには、異なる企業や産業の枠を越えて「共創」し、新しい価値を創出することが求められます。
「地域企業の突破口」では、東北の企業や自治体の先端共創事例を特集していきます。
CASE15 リノベーションで町に人を呼び戻す
土地取引が4倍のエリアに
老若男女問わず、県内外から人の足が絶えない。町の空気を一変させた拠点が秋田市南通亀の町にある。その名も「ヤマキウ南倉庫」。
倉庫の活用事例として名を馳せ、全国から視察が訪れるこの建物は、元は空き倉庫だった。それが今では、年間を通じて多彩なイベントが開かれ、人が行き交う町のハブへと生まれ変わっている。
ビルオーナーによる1億5,000万円の投資を受けて始動し、テナント入居は満室でオープン。そして、施設の運営はテナント入居者自身が自治的に担うという異例のスタイル。「リノベーション・オブ・ザ・イヤー2019」ではエリアリノベーション部門での受賞も果たし、今や南通亀の町は世代を問わず多くの人が交差するエリアとなり、土地取引数は4倍にまで増加した。
手がけたのは、デザイン会社・株式会社See Visions。社長・東海林諭宣さんが2013年、飲食店「酒場カメバル」を立ち上げたことから物語は始まった。やがて、カフェやイベントスペース、コワーキングスペースといった新たな拠点が次々に生まれ、エリアの活性化をけん引。
「自分たちが楽しむ場所を、自分たちの手でつくる」という想いが、町全体を巻き込んだ変化へとつながった。どのようにしてここまでの変貌を遂げたのか、そのストーリーを辿る。

空き倉庫を改装して誕生した「ヤマキウ南倉庫」
誰もやらないから、面白い
「誰もやらないなら自分がやる」──そう決意し、東海林社長は建物のリノベーションを開始。人通りがなくなった通り、買い手のつかない空き家。そこに可能性があると信じた。
空き家をリノベーションしてオープンした「酒場カメバル」は、あっという間に人気店となり、月商300万円を超えるまでに成長。店内で交わされる「この町にこんな場所があったらいいな」という声が、やがて「サカナカメバール」など次の事業へとつながっていった。
「目立たない場所だから逆にニュースになる」という発想のもと、次々に手がけた拠点が地域の人流と景観を大きく変えていった。「エリアリノベーション」という考え方により、点在していた空き家のリノベーションが「点」から「線」へ、「線」から「面」となり、地元の高齢者、若者、ファミリー層が交じり合う風景が町に生まれた。
地元の事業者も新たに店を出す動きが生まれ、年間わずか4件だった土地の取引件数は、2016年には16件に増加した。かつては“見放された場所”だった南通亀の町が、全国から注目を集める地域拠点として復活する瞬間だった。

1店舗目である「酒場カメバル」から物語は始まった
人がつながる“倉庫の中の公園”
2019年、1億5,000万円をかけて旧倉庫から生まれ変わり、テナント入居率100%で「ヤマキウ南倉庫」がオープンした。16のテナントが入居し、カフェや雑貨店、オーガニック直売所など多彩な顔ぶれが彩りを添え、地域から愛される複合施設となっている。
高齢者や若者、ファミリー層までが入り混じるこの空間は、単なる商業施設にとどまらない「共創の場」だ。2階のコワーキングスペースは学生や起業家など、若者の拠点としても活用されている。
この建物の中央にあるのが、「KAMENOCHO HALL KO-EN(コウエン)」、通称「屋根付きの公園」だ。天候を気にせず人が集まり、イベントやワークショップが頻繁に開かれるこの空間は、来場者とテナントのみならず、出店者同士の交流も自然と生む、まさにコンセプトに掲げる「SYNERGY(相乗効果)」を体現する。
「無駄に見える空間が、実は地域のハブになっていく」と東海林社長は語る。地域の誰もがふらっと立ち寄れるこの場所が、地元コミュニティと新たなつながりを育む土壌になっている。

まるで公園のように来訪者が自由に過ごす
自主管理だから加速する共創
ヤマキウ南倉庫では、その運営にすらも共創の姿が垣間見える。
ここでは独自の「自治会制度」という仕組みにより、イベント企画、施設の維持・管理や課題の共有・改善にいたるまで、すべてがテナント入居者によって自主的に話し合われる。設備維持にかかる費用も軽減され、テナントの負担も抑えられるという、全員にとってメリットのある仕組みだ。
「“自分たちの場所”として関わってもらうことで、当事者意識が生まれる」と東海林社長。
トイレ掃除ひとつ取っても、テナント同士が役割分担して行うことで、他人事の空気は一切ない。だからこそ、単なる商業施設ではないコミュニティとしての強さと持続可能性を育んでいる。
実は、テナントは一般公募せず、東海林社長が自ら声をかけ、想いに共感した事業者が入居している。ビジョンを共有した仲間が集うことで、地域のつながりと入居者のモチベーションを高め、ヤマキウ南倉庫は「共に育てる場」としての独自性を確立した。
「町は古くならない」
地域の未来は自分たちで面白くしていける──。共に考える仲間を集め、関わる人たちと楽しみながら一緒に育てることを大切にしてきた東海林社長。
ヤマキウ南倉庫を起点に、町にはマーケット「亀ノ市」やナイトイベント「亀の町夜市」、新春恒例の「新春市」など、多様なイベントが定着した。地域内外から人が訪れ、買い物や対話を楽しむ空間が育っている。
実は、旧倉庫の所有者であるヤマキウビルのオーナーは、出会った当初は門前払いだった。しかし、町の変化に次第に心を動かされ「自分もこの町の面白さに関わりたい」と思うようになり、挑戦を後押しする存在へと変化。
その結果、オーナー自身が倉庫のリノベーション総工費1億5,000万円を出資するに至り、ヤマキウ南倉庫プロジェクトが始動。世代を越えた共感が町の未来を後押しした。
「町は古くならない」と東海林社長は言う。時間が経っても、想いを共有する人たちが関われば、町は更新され続ける。その言葉通り、ヤマキウ南倉庫は今もなお新たな物語を生み続けている。
東海林社長が見据えているのは、投資資金を完済する10年後、 ヤマキウ南倉庫を起点に新たな事業やプロダクトが誕生する未来だ。
地域再生に必要なのは、町を愛し、面白がり、共に育てようとする人々のつながりだろう。ヤマキウ南倉庫はその確かな実践例として、秋田の一角から全国に問いかけている。

取材時の様子(左:トークネット 菅原 中央:See Visions 東海林社長 右:雑談会議 稲垣)
インタビューの全編動画を会員限定で公開中!
▼ ご興味のある方はぜひご覧ください ▼
『CONNECT+』ではいろいろな情報を発信していきます。
会員登録は無料ですので、まだの方はぜひこの機会にご登録ください!
|
<サービス提供者について> |