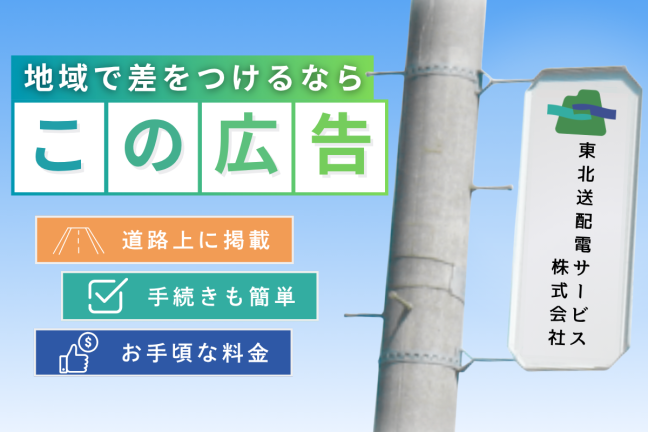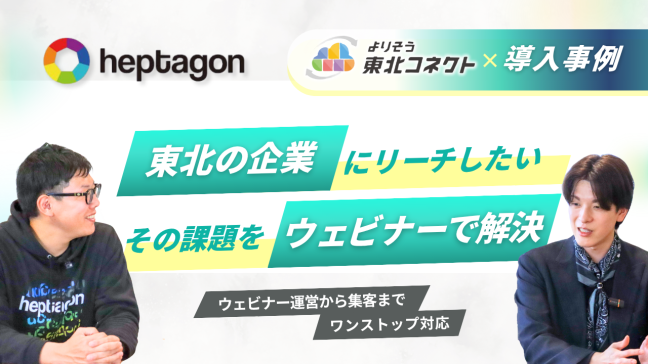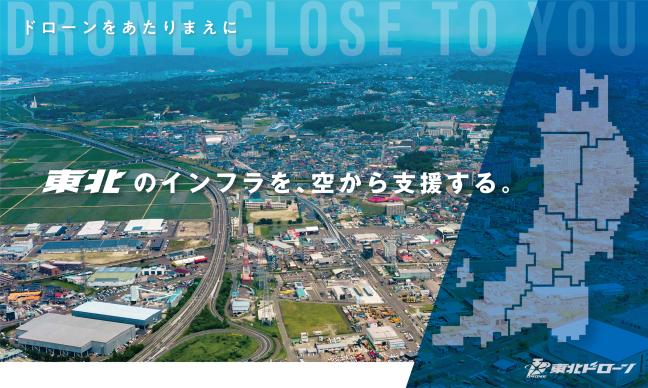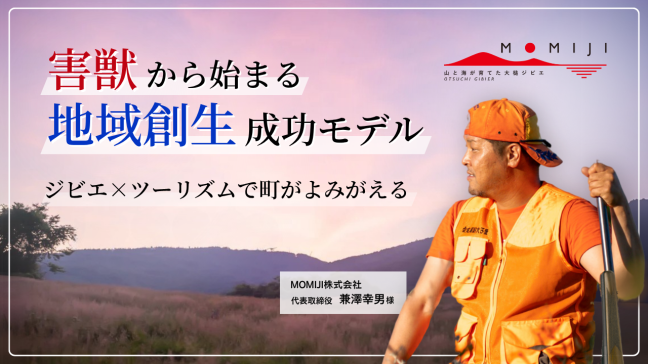『CONNECT+』Vol.16:地域企業の突破口
- イノベーション・共創
- 地域活性化・地域課題解決
- CONNECT+
- 東北・新潟の地域活動や社会貢献活動に参加したい
掲載日:2025年10月17日

地域企業の突破口
~共創からはじまるInnovation~
「共創」は企業にどんな変革をもたらすのでしょうか。
地域企業が成長し続けるためには、異なる企業や産業の枠を越えて「共創」し、新しい価値を創出することが求められます。
「地域企業の突破口」では、東北の企業や自治体の先端共創事例を特集していきます。
CASE16 異業種共創で地域の未来に挑む
異業種集団が街を再生
創業100年を超える老舗企業を母体としながら、異業種21社を束ねる異色の集団がいる。「大島グループ」は、地方経営の常識を覆す存在だ。
赤字事業を買う常識外れのM&A戦略ながら、年間4万人が訪れる「浄興寺大門通りスクエア」のエリア開発に成功。業種を超えて経営者同士が学び合う仕組みを整え、地域を動かす新たなリーダーを次々と輩出するなど、その躍進は止まらない。
異業種多角化は「高リスク」とされるのが定説だ。それなのに、なぜ無関係に見える事業群が一体となり、成果を出し続けられるのか。どのようにして、負の遺産を資産へと転換しているのか。
「生き残る地方」をつくるため。都会よりも一歩進んだ田舎を目指し、地方に革新を起こす異業種集団「大島グループ」。その秘密をひも解くと、地方再生の未来が見えてくる。

大島グループの原点である「大島自転車商会」(1922年創立)
常識と真逆のM&A戦略
事業を買う基準は「利益」ではなく「必要」にある—―。一般的なM&Aは「儲かる事業を買う」ことが常識だが、大島グループは真逆だ。
2013年に承継した老舗料亭「宇喜世」は、その象徴である。客足が途絶えて廃業寸前だったこの場所に、大島代表は「街の象徴を絶やすわけにはいかない」と手を差し伸べた。
全国の百年料亭とのネットワークを構築し、商店街を巻き込んだ催事を展開。来訪者は5年で2.5倍に増え、地域を代表する観光資源へと変貌を遂げた。
「赤字でも地元に必要なら引き受ける」大島代表のもとへ持ち込まれる承継の相談は収益性に乏しい事業が多いというが、地元に不可欠であると判断すれば、リスクを承知で引き受ける。
収益性を求めて、各地で大手チェーンのような均一化が進む中、地域独自の「その土地ならでは」を守ることこそ、長期的に価値を生み出す道だと信じているからだ。
「生き残る地方」に必要なのは、短期的な利益ではなく、本当に必要なものを見極めることにあるのだろう。
老舗料亭「宇喜世」は国登録有形文化財に登録されている
トップを育てる仕組み
事業を承継するだけでは街は変わらない。そこに「人づくり」の仕組みが加わって初めて再生が始まる。
大島グループでは、各社の社長は外部から呼ばない。現場を知り尽くした人材がトップに立つことで組織は強くなるからだ。
経営に集中できるよう、本部が投資や資産の所有を担い、借入金の返済負担を軽減する体制も整えられている。社長は資金繰りに追われることなく、本業と未来の事業づくりに注力できる。それでいて、各社が孤立しているわけではない。グループ内の企業を超えて学び合う文化が醸成されているからこそ、次々と新しいリーダーが誕生するのだ。
「経営者とは儲ける人ではなく、未来に投資する人」と大島代表は語る。この言葉通り、地域で次世代のリーダーを育てる土台となって街の再生を担っている。
個性的で独創的
大島グループには、チョコレート店を運営する学習塾がある。「学習塾がなぜチョコレート?」と疑問に思うだろうが、その背景には、教育から就労までを一貫して支える仕組みがあった。
学習塾「井手塾」は、放課後等デイサービスの立ち上げを経て、発達障害を持つ子どもたちへのサポートを長年続けてきたが、卒業後に働く場が不足している現実に直面していた。そこで、障がいのある若者が働ける場として、愛知県に本社を置く『久遠チョコレート』のフランチャイズ運営を開始した。これにより、塾から就労へという循環を生み出し、教育・福祉・ビジネスを有機的につなげるモデルを築いた。
グループ内外を問わず、価値観を共有できるブランドと積極的に手を結び、異業種を越えて事業を展開。常に「必要だからやる」という一貫した軸を持ち、独創的な市場を開拓することで、他にない存在感を示している。

大島グループ 井手塾がFC運営する「QUONチョコレート&DEMI-SEC 新潟上越店」
10万人構想
年間4万人の来訪者を呼び込む「浄興寺大門通りスクエア」だが、次の目標は大きく10万人。単なる数字の拡大ではなく、地域経済全体の活性化を見据えた挑戦だ。
若手経営者チームのプロジェクト推進により、歴史ある建物のリノベーション、ワーケーションオフィスやミニマムホテルを開設する計画も進む。「寺カフェ」といった新たな業態も構想にあり、観光客の滞在時間を伸ばす仕掛けを次々と仕込んでいる。さらに、地域産業や商店街と連携した協賛会を設立し、エリア全体を一体化し、黒字化する街を築こうとしている。
「10年後、自分は引退しても、若い世代が次々に新しいプロジェクトを立ち上げ、地域に寄り添いながら未来をつくってほしい」。大島代表の言葉からは、世代を超えて豊かさを紡ごうとする想いがにじむ。
事業承継から人づくり、そして地域づくりへ。大島グループは、「必要」を基準に生き残る地域の姿を描き出していた。ローカルの未来に必要なのは、都会への追従ではなく、「地方だからこそ」の価値を追及することではないだろうか。
左:トークネット 太田 中央:大島代表 右:トークネット 菅原
インタビューの全編動画を会員限定で公開中!
▼ ご興味のある方はぜひご覧ください ▼
『CONNECT+』ではいろいろな情報を発信していきます。
会員登録は無料ですので、まだの方はぜひこの機会にご登録ください!
|
<サービス提供者について> |