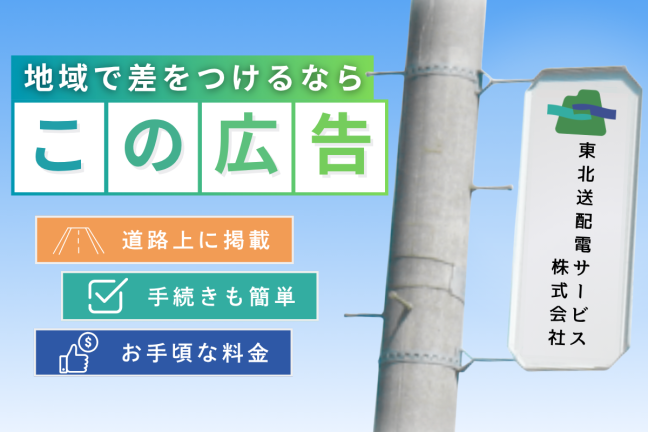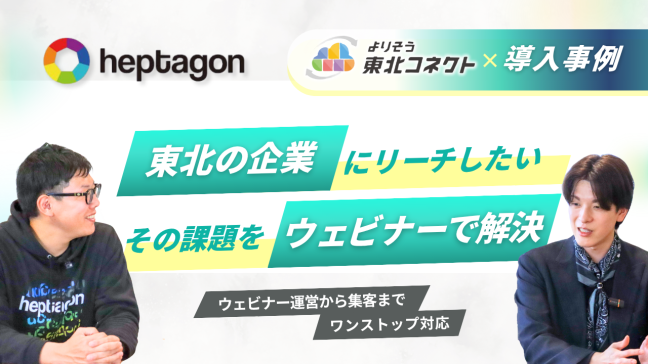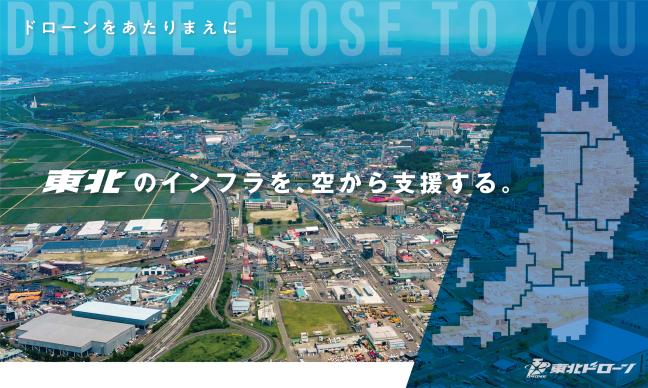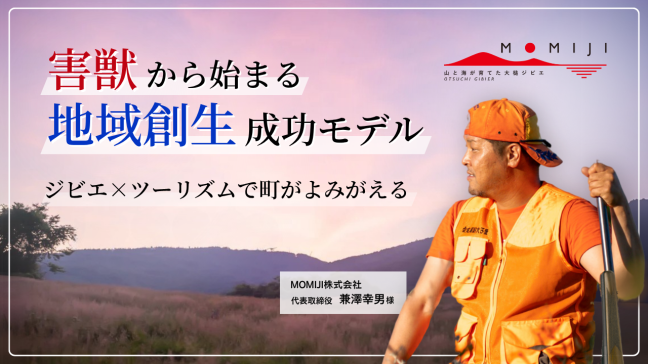『CONNECT+』Vol.4: 地域突破口【マルリフーズ】
- 地域活性化・地域課題解決
- イノベーション・共創
- 地域情報
- CONNECT+
掲載日:2024年3月29日
地域企業の突破口
~共創からはじまるInnovation~
「共創」は企業にどんな変革をもたらすのでしょうか。
地域企業が成長し続けるためには、異なる企業や産業の枠を越えて「共創」し、新しい価値を創出することが求められます。
「地域企業の突破口」では、東北の企業の先端共創事例を特集していきます。
年間出荷ゼロから、海外進出までの軌跡
CASE04 共創であおさの概念を打ち破る
松川浦のあおさと漁港
“すてっぱず”とは、福島県相馬市の浜言葉であり、“ものすごい”という意味だ。福島県相馬市で、あおさの生産者・地元の加工会社・宿泊業者がタッグを組み、“すてっぱず松川浦”という新ブランドを立ち上げ、世界をめざす人たちがいる。県内唯一の潟湖である松川浦であおさを生産する漁師の一人、遠藤友幸氏。あおさ一筋で独自の高い洗浄技術を持つ株式会社マルリフーズ(代表取締役 稲村利公氏、営業部部長 阿部純也氏)。そして、松川浦を代表する観光旅館・ホテル飛天を経営する管野貴拓氏だ。
東日本大震災により、7年もの間、松川浦産のあおさが生産も出荷もゼロになるという誰も経験したことがない壁を前に、異業種の彼らが手を組むことで立ち向かい、地域に誇りを取り戻しつつある。
異業種 × 共創 × 復興
三者が手を組むきっかけとなったのは、7年間の空白により「松川浦であおさがとれることを地元の人も良く知らない」という自体に陥った危機感からだった。そこに追い打ちをかけたのは風評被害による福島の水産物に対するマイナスなイメージだった。
は、その大きな壁を乗り越えるために、会社や立場を超えて「地域一体となってPRする」ことが福島の復興につながる、という共通のゴールを描いた。そのための手段として、2020年10月に漁業と生活者を結ぶ「相馬復興市民市場(浜の駅松川浦)」がオープンすることに合わせて、新ブランド“すてっぱず松川浦”を立ち上げ、新商品開発がスタートした。
あおさを用いた様々な商品について語る阿部氏(株式会社マルリフーズ 営業部部長)
遠藤氏が良質なあおさを生産し、マルリフーズが業界トップクラスの洗浄・異物除去技術でさらに高品質なあおさに加工。乾燥あおさ以外の商品は、県内の事業者とコラボし、あおさの様々な加工商品を生み出した。そして、管野氏が浜の駅や旅館を拠点に、観光客や地元の人たちにあおさの新しい食べ方を提案しながら、届ける。
生産から加工、販売までの一連を一貫して行う取り組みとあおさの概念を打ち破る商品で、高齢層にとどまらず若年層まで購買層が広がった。「松川浦産のあおさ」が確実に認知され、あおさの商品を目当てに浜の駅や道の駅を訪れる地元の人や県外の旅行者も増えた。
危機感から「共創」へ
元々、海外旅行に一緒に行くほど、ものすごく仲がよかったという彼ら。「何か手を打たなければ」と逡巡する中で、本音を言い合える仲間がいたことが支えとなった。三者で共通の危機感とゴールを共有したことが鍵となり、「松川浦のあおさを取り戻したい」という強い想いが、商品開発の実現と認知度の向上につながった。
浜の駅をはじめとする販売先では、消費者の反応やニーズを確かめ、さらなる高みを目指して三者で対話を重ね、商品やPR方法のブラッシュアップを続けている。

松川浦のあおさを用いた様々な商品の開発
さらに、ブランドづくりで大切にしてきたことは、特産品のあおさと地域のイメージを結びつけるために「相馬」や「松川浦」を強調したことだ。例えば、商品名を「かけるあおさ」ではなく「松川浦かけるおあさ」とするなど、地名を入れること。「松川浦で、美味しいあおさが獲れる」という認知の復活は、福島の水産物のイメージを回復させるだけではなく、あおさ漁師や水産業に関わる人々のやる気や誇りを取り戻すことにもつながっている。それが長期的な福島の復興には大切なことであり、大きな壁を着実に乗り越えつつある。
共創は「信頼関係」から始まる
ゼロをプラスに転換するために彼らが追求したことは、「ほんもの」であることだ。一般的に、海藻の水揚げでは、小さな貝類や釣り具のテグス、鳥の羽など、異物が必ず入り、それらを取り除くことは非常に難しい。そのため、遠藤氏は、あおさの養殖棚に使用する紐をミクロなごみが出にくい紐に替えるなど試行錯誤し、生産の段階から異物を極力減らしていく工夫を凝らす。
そして、マルリフーズは震災前から培ってきた技術と経験で、どんなに小さい異物やごみも徹底的に除去し、高品質のあおさを製造する。こうした生産から加工において両者が協力しあうことで、あおさ本来の風味や食感、美しさを保ちながら、安心してそのまま食べることのできるほんもののあおさを作ることができる。
彼らは、そのほんものをどこまでも追求し続けている。

製造工程の一部。異物を徹底的に除去する
震災を乗り越え、海外へ
ゼロになったものをプラスに転換するという壁を超えた彼らが新たに挑んでいるのが、あおさの海外輸出だ。
あおさの養殖産地は、世界的に見ても限られている。
また、そもそも海外では黒い食べ物や海藻を食べる文化がなく、あおさの存在自体、ほとんど誰も知らない。
そうした層にアプローチし新たな需要を掘り起こすことで、さらに認知度を高め、福島の復興につなげることが大きなねらいだ。
海藻を食べる文化がない層への壁をクリアにしたのは、あおさを使ったメニューの提案だった。
海藻の中でもあおさは緑色のため、それを生かすことで差別化ができるのではないかという視点だ。
あおさをそのまま提供しても手を出しづらいが、和・洋・中など、海外の文化や慣習に合わせたメニューを提案することで、あおさの色味が食卓を彩るというプラスの印象に変化し、日常で食すイメージを持ってもらえることができたのだ。

「ふくしま満天堂」で最高賞を受賞した「松川浦かけるあおさ」
2023年7月にはオランダのバイヤーを県内に招へいし、同年10月に、松川浦産のあおさが震災後初めてEUへ輸出されることが決定。
冷凍でパック詰めされた「生あおさ」がオランダに輸出され、「豊かな風味」「料理の幅の広さ」「冷凍で1年ももつ」という点で高い評価を得た。
徹底的に安全安心にこだわり、“ほんもの”を追求した結果が、衛生管理の基準が厳しいと言われるEUへの輸出へと結びついたのだ。
海外のバイヤーからは、「知られていないものを供給する面白さ」においてもさらに注目が集まっている。
2024年1月、福島県の6次化ブランドで特に優れた商品を表彰する「ふくしま満天堂」で、「松川浦かけるあおさ」が最高賞のグランプリを受賞。
これまで追求してきた成果が実を結んだ。
三者の想いから始まった小さな動きが、海外へと大きな動きに広がり、福島の水産業を大きく盛り上げている。
これからもさらに、「誰も知らない」という壁を突き破り、新たな文化を世界に広げていくだろう。
インタビューの全編動画を会員限定で公開中!
▼ ご興味のある方はぜひご覧ください ▼
『CONNECT+』ではいろいろな情報を発信していきます。
会員登録は無料ですので、まだの方はぜひこの機会にご登録ください!
|
<サービス提供者について> |