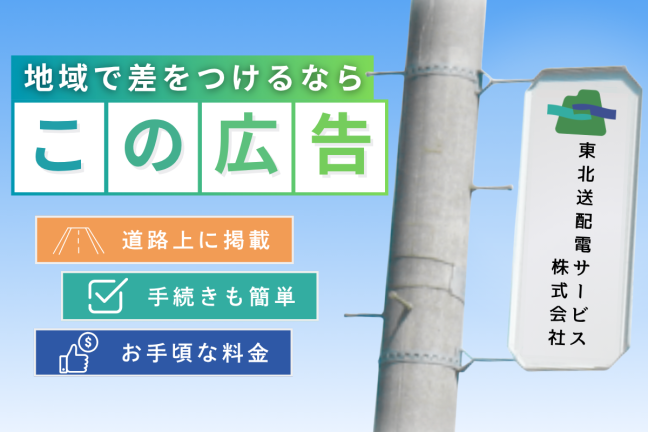『CONNECT+』Vol.7:特別インタビュー
- 地域活性化・地域課題解決
- イノベーション・共創
- CONNECT+
- 東北・新潟の地域活動や社会貢献活動に参加したい
掲載日:2024年8月8日

無名のスタートアップが、世界にその名を轟かせる
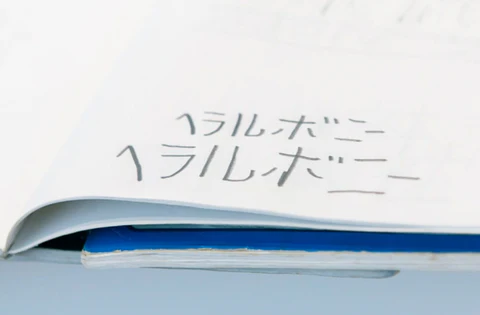
「ヘラルボニー」。耳馴染みのない単語に、はじめは戸惑った人もいたのではないだろうか。
それが今や、メディアで聞かない、見かけない日はないほどの企業として急成長した。
2024年5月には「LVMH Innovation Award 2024」で日本初の「Employee Experience, Diversity & Inclusion」カテゴリ賞を受賞した。
このプログラムは、ルイ・ヴィトンやクリスチャン・ディオールなどのメゾンを傘下に持つ世界最大の複合企業LVMHが、世界各国の革新的なスタートアップを評価するために設立したもの。
ヘラルボニーが示すまったく新しい価値観は、日本という枠組みを超えて世界でも評価されていることを裏づけている。

言葉を研ぎ澄まし、ぶれない原点を確立した創業期
「異彩を、放て。」をミッションに掲げるヘラルボニーは、2018年7月、重度の知的障害を伴う自閉症の兄を持つ双子の松田崇弥氏・文登氏が、障害のイメージの変容を目指して設立した。
ヘラルボニーという社名は、兄・翔太さんが小学生の頃にノートに記していた謎の言葉が由来である。
同社では、主に知的障害のある作家のこだわりや才能を「異彩」と捉え、彼らとライセンス契約を結び数々のアート作品を世に生み出している。


「社会的に意義のある活動だ」と誰しもが口にするだろう。
しかし、それだけではビジネスにならない。
事実、設立後1~2年目頃までは「厳しい状況が続いた」と、文登氏は語る。
では、その売れない2年間に何をしたか。
ヘラルボニーは決してぶれない価値観を確立し、それを表現するための言葉を研ぎ澄ました。
つまり、徹底的なブランディング戦略を練りに練ったのだ。
言葉が企業の土台をつくり、価値を社会へ届けるという観点から、マーケットフィットよりも先に社会的なフィットを目指したのだ。
こうした創業期のブランディング戦略は「どこの企業にとっても必要かもしれない。」と文登氏は語る。

共に社会を変革し、未来へ向かって走ることこそが共創
創業期に原点を確立したヘラルボニーは、その後もコツコツと地道に活動を続け、徐々にその地位を確立させていった。
作品の展示やアートを取り入れたファッションアイテムの販売など、自社で単独での事業を拡大するだけでなく、数々のナショナル企業とのコラボレーションもおこなってきた。
これらの共創事業は、単にアート作品を販売するだけではない。例えば、ウォルト・ディズニー・ジャパンとのコラボでは、「Love Difference.」(ちがいを愛する)をコンセプトに、特別なアート作品を制作し、多くのファンを魅了した。
また、JALとは企業として多様な価値観を尊重し合える社会の実現を目指す方向性が合致したことから、業務提携が実現。
特別な機内アメニティやイベントが実施され、多くの利用者から好評を得ている。

設立から10年足らずのスタートアップがこうした大躍進を遂げた背景にあるのもまた「言葉の力」だ。
「ヘラルボニーを、いかにして『仲間に入りたい』と思ってもらえる企業にするか、という点を強く意識してPRしています。障害のイメージを変えたいと創業しました。だからこそ社会を変えたいという強い意志を示す必要があります。そのためには、より多くの人に『刺さる』言葉を選び、効果的に発信していかねばなりません。」
実際、ヘラルボニーの共創事業は、3年後の未来を見据えて計画されているそうだ。一過性の事業で終わるコラボではなく、共に社会を変革し、歩んでいけるパートナーと仕事をしたいと考えているためだ。


ローカルから世界へ 古き良き歴史を語り継ぎ、新しい文化を創造する
今や全世界から注目を集めるヘラルボニーの創業の地は、岩手県盛岡市。
城下町として知られ、古くから栄えた歴史のあるまちだ。
ニューヨーク・タイムズ紙「2023年に行くべき52カ所」で、ロンドンに次いで2番目に紹介されたことも記憶に新しい。
この場所でヘラルボニーが成そうとしている目標は、大きく2つ。
価値観やカルチャーの醸成と、地域の魅力を世界へ発信することだ。
盛岡市内には、ヘラルボニーのアート作品を鑑賞できる常設展やグッズを購入できる常設店が設置されている。
売上だけ見れば、東京への出店やナショナル企業とのコラボ事業の方が遥かに高い。

しかし盛岡で活動することの意義は、単なる利益の追求ではない。
創業の地にヘラルボニーの目指す価値観やカルチャーを根づかせ、醸成することだ。
時間はかかるが、地道な活動がいずれ社会を良くすることにつながり、結果的に共創などのビジネスにおいても良い結果をもたらすと考えている。
もう一つの目標が、地域の魅力発信だ。
東京など県外から企業が訪れた際は、南部鉄器をはじめとする特産品など、必ず地域のプレイヤーや暮らしを紹介している。
こうすることでヘラルボニーだけでなく、まち全体を押し上げていくことにも寄与している。
ヘラルボニーが目指す100年後の未来

今から100年後の未来を想像してみてほしい。
障害のある人が、同じ職場で一緒に働いている。ヘラルボニーが目指すのは、それがスタンダードであり普遍的な価値観となった社会だ。
現在では、障害のある人が働く姿は一般的とは言えず、特別なものとして捉えられがちだ。
しかし同社が100年にわたりこの活動を続けることで、それが「普通」の風景として社会に浸透するのではないだろうか。
これは単に一つの企業としての目標にとどまらず、社会全体に新しい価値観を根づかせるための挑戦である。
シニアマネージャーの木村芳兼は「ヘラルボニーの価値観に賛同する企業が地元岩手で増えることを目標に日々コツコツと活動しています。それにより盛岡という地に根付く企業になると思うからです。」と笑顔を見せた。
「変革の追求そのものが正解なのではない。ヘラルボニーがどう正解にしていくかを常に自分たちに問い続け、より良い未来に向かって歩み続けなければいけない」という文登氏の言葉が印象的だった。
ヘラルボニーはこれまでになかった新しい価値観を創り、社会を変革している。
まさに今、大きなうねりを生みながら世界が変わっていく。
我々は、その過渡期に立ち会っているのかもしれない。
『CONNECT+』ではいろいろな情報を発信していきます。
会員登録は無料ですので、まだの方はぜひこの機会にご登録ください!
|
<サービス提供者について> |